台木について
台木が穂木品種に及ぼす影響
台木品種(根の品種)は穂木品種(地上部の品種)に様々な影響を与える。
しかも、交配された台木品種は数も多く、それぞれ特性を持つ。
また、同じ台木品種であっても、穂木品種によってはその影響が異なるし、
栽培地や栽培条件によって影響が異なることもあるようだ。
「果樹園芸大百科3 ブドウ」から引用すると、
「一般に台木は穂木品種の樹勢、樹の拡大性、結果性、樹齢、結実の良否、
収量、成熟期、着色、糖度、果粒肥大、裂果性、日持ちなど
ブドウ生産の全面にわたり、さまざまな影響を及ぼすと考えられている。」
ということになる
台木の三大原種
以下、「果樹園芸大百科3 ブドウ」と「日本ブドウ学」から引用。
——————————————————————-
リパリア種
リパリアは「リバーサイド・グレープ」と呼ばれるように、
河岸の湿潤地帯に自生している野生種で、
湿地、酸性土壌に強く、
台木に使用すると穂木はあまり大きくならない矮化性台木で、
台負けしやすい。
根は細く浅く、向地角(垂直線と根の角度)は
80度程度で地表をはうように根が伸び、土中に深く入らない。
地温は地表面から上昇するので、春は早くから根が活動を開始する。
このため、果実は最早熟になり、品質も向上する。
発根も良く、繁殖は容易である。
根が本来浅いので乾燥には弱く、
根の伸張も少ないので収量も少なく、したがって樹齢も短い。
リパリア・グロワール・ド・モンペリエが代表品種である
ルペストリス種
ルペルトリスは「岩ブドウ」と呼ばれ、砂礫乾燥地に自生している。
リパリアがわい化性であるのに対して、
ルペルトリスは喬化性台木であって台負けせず、
穂木品種を広げる性質である。
根は強く、深根性で向地角は20度程度であり、
直下に深く根が伸びるので、乾燥抵抗性は最も強く、
量産・頑健である。
しかし、根が深いので地温の上昇が遅れ、
晩熟となり品質もあまり良くなく実止まりもよくない。
また、湿地では地下水が高く、根腐れを起こしやすく耐湿性は弱い。
ルペルトリス・デュ・ロットが代表品種である。
ベルランディエリ種
ベルランディエリは乾燥した山頂部や傾斜地に自生し、
石灰抵抗性が強く、ヨーロッパでは特に重要な台木である。
わい化性で早熟、しかも放散で品質向上性が高く、樹齢も長い。
向地角は30度程度で根は深く、太く、乾燥抵抗性が強い。
リパリアやルペルトリスに比べると育苗時の発根、活着が困難である。
代表品種にレッセギー1号、2号がある。
——————————————————————
主要台木品種
日本での人気は、乾燥にも湿潤にも耐える、
適応性の強い5BB、5C、8Bのテレキ系3大品種。
なかでもテレキ5BBが人気の中心で、
果実の品質も良く、早熟で果粒の肥大、着色が優れている。
北海道などの寒冷地では耐寒性の観点から5Cにも人気がある。
また、適湿肥沃地や火山灰土壌などでは101-14にも人気がある。
フランスでの採用実績は以下。1976年の資料。
1位:ルペルトリス・セント・ジョージ
2位:グロワール
3位:3309
4位:41-B
5位:161-49
6位:99R
7位:SO.4
8位:5BB
9位:110R
10位:420A
そして、現在使われている台木品種の特性を。
「果樹園芸大百科3 ブドウ」をベースに追記した。
主要台木品種の特性
リパリア・グロワール・ド・モンペリエ
リパリアの純粋種である。
台木品種の内、最も早熟で若木から良果を産し、
着色が良く、品質は高い。
適湿な砂質の肥沃土壌で、深度のある土壌を好む。
樹勢が弱く、台負けが甚だしいので、優良台木とはいえない。
凍乾害には注意が必要で、なりすぎは禁物であり、
乾燥やせ地には向かない。
栽植本数は3割~5割増しとし、やや密植する方がよい。
地中の活性石灰に対する耐性率6%。
101-14
リパリアとルペストリスの交配系統中では、最もリパリアに近似し、
グロワールに次いで早熟であり、幼木から良果を産し、
品質も良好である。
わい化性にもかかわらず、台負けの程度は軽く、
樹勢もグロワールより強く、適地の幅も広い。
優秀台木で、早く収穫を望みたい品種などには101-14が最も良い。
火山灰土壌では樹勢を落ち着け、最適種である。
湿気が多い土壌にも良くなじみ、ゆっくりと乾燥させていく。
土中の活性石灰に対する耐性率9%。
101号は同系統でやや樹勢が強いほか、ほぼ性質は同じである。
188-08号はモンティコラとリパリアの交配品種で、
101-14と形質や葉形が似ている優良品種だが、
繁殖が困難で普及していない。
3309
リパリアとルペストリスの交配系統のなかで、
ルペストリスの性質に最も近く、乾燥抵抗性が最強である。
やや晩熟だが台負けが少なく、
デラウェアや甲州の台木として人気が高い。
他品種では台負けと晩熟性のためテレキ系台木の方が好まれる面もある。
豊産で品質、着色ともに優れ、樹齢の長い優良台木であり、
ハウス栽培では強さを発揮する。
しかし、台木そのものは旺盛に伸長せず、挿し木がとれない欠点がある。
気候の不順に対して上部だが、樹勢は平均的。
穂木をしっかり成熟させるため、
高級ワイン造りに必要な良質の要素の1つとみなされている。
土中の活性石灰に対する耐性率11%。
3306
リパリアとルペストリスの交配系統で、3309の兄弟品種だが、
湿地に強く対照的である。
田跡地などの砂地、粘土ともに敵視、乾燥地でも生育がよい。
3309より早熟で品質も良く放散である。形態もよく似ているが、
新梢や葉柄上に繊毛が密生し、鑑別できる。
それでも品質向上性、早熟性、適地の幅の広さなどの点から、
テレキ系台木の方がより優秀であるため、
リパリアとルペストリスの交配系統は
テレキの人気に押されてやや後退しつつある。
テレキ8B
ハンガリーのテレキ氏は、
ベルランディエリとリパリアの多量交配を行って、
4万粒の種をまいて生えたもののうち16種を選抜し、
なかでも優秀として選抜したのがこのテレキ8Bである。
8Bは交配種中で最もベルランディエリに近く、
着色、粒張り、品質向上性が優れ、幼齢期から良果をつけ、
収量も多く樹齢も比較的長いため、現在でも最高の優良台木と言って良い。
準わい化性であるが、穂木品種の拡性は大となり、
肥沃地では徒長的になりすぎるきらいもある。
土壌適応性は広く、乾燥地から湿地に適し、
砂礫土から粘土まで広範囲に適地を持つことが強みである。
欠点は徒長的な欧州種に接ぎ木すると台負けが激しいこと。
繁殖の際の発根が悪いことである。
8Bは他のテレキ系台木と比較すると、
枝梢上にビロード状に密生する繊毛で容易に鑑別できる。
また、実のなるものは真の8Bではない。
テレキ5BB
テレキ系台木の中からコーベル氏が選抜したもので、
8Bよりはリパリアに近い性質である。
台負けはするが、8B、5Cよりは程度が軽く、
やや浅根だが根は太く拡性があり乾燥には強い。
樹勢も強く若木のときは徒長しやすいが、成木になれば落ち着く。
湿地では8B、5Cに劣り、土層の深い乾燥地が適地である。
テレキ系台木のうち最早熟で、グロワール、101-14に次ぐ。
着色が良く、果粒の肥大もよく品質向上性が高い。
日本では普及率第1位の台木品種で、現在もなお人気が高まっている。
フランスでは古くなって引き抜いたブドウ樹の代替として、
畑や区画の一部に植樹する場合に最適とされている。
土中の活性石灰に対する耐性率20%。
テレキ5C
準わい化性台木だが比較的、
深根性で根が太く樹冠を拡大させる点は8Bに似ている。
5BBよりも一般的に樹勢は弱く、比較的早く育つ。
若木の時は徒長するので、品種によっては台負けが甚だしく、
また火山灰土壌では徒長しやすい。
土壌適応性の幅は広く、湿地向き台木といわれていたこともあるが、
乾燥にも強く、8Bに勝るとも劣らない。
品質向上性もあり、早熟、豊産で優秀である。
特に耐寒性が優れ、中部ヨーロッパからドイツなど北部では5BB、8Bより
5Cの方が広範囲に利用されており、
日本でも北海道などで耐寒性の強さが認められ人気が高く、
その一方で九州などでも土地が適し、使われている。
8Bの発根が困難なのに比べ、5C、5BBは発根、活着が良く、
普及性を高める一助となっている。
5Cは葉が大きく、無毛で実を結ばない。
丘の斜面上部などの痩せた土壌に非常にうまく適合する。
土中の活性石灰に対する耐性率20%。
S.O.4
セレクション・オッペンハイムNo.4の略称。
非常に生育が早く、早熟性である。
耐乾性が特に強く、5BBに似ているが、耐湿性もあり、
肥沃な粘土質土壌に適す。
豊産で品質優良、根は堅く強く中深である。
土壌適応性も広く、樹冠は拡大する。
準わい化性台木で生育が旺盛。
期待は高かったが、台負けと育苗の不安定さから人気は落ちてきている。
土中の活性石灰に対する耐性率18%。
420A
テレキ系と同じくベルランディエリとリパリアの交配だが、
420Aはフランスで交配されており、テレキ系とは呼ばない。
ベルランディエリの性質を良く受け継ぎ、耐寒性が最も強く、
品質向上性があり、早熟である。
耐湿性は弱いが耐乾性が強く、石灰抵抗性も強い。
このため、ヨーロッパでは重要な台木となっている。
樹勢が控えめであるため、
「リパリア・デ・テール・カルケール=石灰土壌のリパリア」
と呼ばれている。
痩せた土壌ではすぐに枯れてしまうので厳禁。
土中の活性石灰に対する耐性率20%。
ルペストリス・デュ・ロット
樹勢が強いため、花ぶるいを起こす特定の品種に向いている。
湿気のある土壌には危険。
土中の活性石灰に対する耐性率14%。
161-49
異状樹脂分泌病に対する敏感さから一時期見捨てられていたが、
場合によっては、その他の台木には不可能な最上の結果が得られる。
結実を促し、樹勢は限られている。
グラン・クリュ向きの台木。
土中の活性石灰に対する耐性率25%。
RSB1
平均的な樹勢。ブドウに豊かな糖度を与えてくれる。
乾燥に強く、過剰な湿気に対しても耐性がある。
土中の活性石灰に対する耐性率20%。
99Richter
根が匍匐(横に伸びる)しやすい。
樹勢は平均から強め。
乾燥に対する耐性が110Richterより低いため、
使用頻度が低くなっている。
土中の活性石灰に対する耐性率17%。
110Richter
乾燥に対して非常に高い耐性がある。
粘土石灰質で密度の高く、深度があまりない土壌に良く適合する。
中庸な樹勢で、結実を促進し、
地中海沿岸の地域での良好なブドウの熟成を可能にしてくれる。
土中の活性石灰に対する耐性率17%。
140Ruggieri
気候の不順に対して非常に上部で、傑出した樹勢。
乾燥して痩せた石灰質の土壌において素晴らしい結果を出す。
湿気が多い土壌には向かない。
ブドウの成長サイクル全体を少し長くする傾向にある。
土中の活性石灰に対する耐性率20%。
1103Paulsen
強い樹勢で,鮮度石灰質の土壌に良く適合する。
乾燥にも湿気にも抵抗力がある。
乾燥にはしっかりとした耐塩性がある。
土中の活性石灰に対する耐性率19%。
ヴィティス・ベルランディエリとヴィティス・ヴィニフェラの交配品種
41B
石灰土壌の台木。
結実力が良好だが、熟成を少し遅らせる傾向にある。
乾燥にはしっかりとした耐性があるが、湿気には抵抗力がない。
土中の活性石灰に対する耐性率40%。
FERCAL
萎黄(イオウ)病に対し、非常に耐性がある。
樹勢が強く、しっかりとした熟成を促す。
マグネシウムの欠乏に対し非常に敏感。
土中の活性石灰に対する耐性率40%。
GRAVESAC(グラヴサキ)
3309と161-49の交配に由来する品種。
樹勢が強く、質の高い台木。
砂質や砂利質の土壌に非常に良く適合する。
土中の活性石灰に対する耐性率25%。

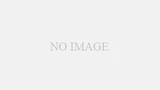

コメント